新学長に聞く
「真摯な学び」を追究し、新たな青学ブランドの構築を目指す
2023年12月16日、前副学長の稲積宏誠教授(社会情報学部)が学長に就任しました。変化する時代の中、新体制ではどのような大学の姿を目指すのでしょうか。直近の取り組みから将来的な構想まで稲積学長が語りました。

稲積 宏誠(いなづみ ひろしげ)
1956年生まれ。岡山県出身。工学博士(早稲田大学)。1984年 3月 早稲田大学大学院理工学研究科機械工学専攻博士前期課程修了。専門分野は情報理論、人工知能、機械学習、日本語教育。
青山学院大学理工学部 経営工学科、同情報テクノロジー学科助教授を経て、2003年同情報テクノロジー学科教授に就任。2004年理工学部長、大学院理工学研究科長。2009年社会情報学部 社会情報学科教授に就任。2010年社会情報学部長、大学院社会情報学研究科長、2019年副学長を歴任。2023年12月青山学院大学第20代学長に就任。任期は2023年12月16日~2027年12月15日。
 新学⻑インタビュー
新学⻑インタビュー
■ 研究・教育環境の充実を図り、最新の学びから「学び直し」までを推進
社会全体に急激な少子化の波が押し寄せる中、大学にもさらなる改革が求められています。こうした状況において、学長としてのミッションは、本学が今後もサステナブルで魅力的な大学であり続けるための体制づくりであると考えています。そのためには10年後、20年後まで見据えた取り組みが求められています。本学はこれまで「都会的でおしゃれ」といったブランドイメージが対外的な強みとなってきました。これは「明るく自由」という意味で、高度経済成長期の激しい競争社会においては他大学との違いを明確化する意味で貴重でした。しかし、現在の若者の受け止め方はことさら「軽い」「遊び」のみが先行し、従来のそれとは違っているように思います。特に、大学受験世代の人口が減り続ける中、研究・教育・社会貢献という本来的な大学の価値を保ち「選ばれる大学」であり続けるためには、本来の多様性を重視した「明るく自由」という意味での「都会的でおしゃれ」に加えて、これまで以上に「真摯な学び」に重きを置いた新たな青学ブランドを構築していくことが重要です。そのための研究・教育の取り組みとして、今私が考えていることをお話しします。

第1点めは「大学院を中心とする研究・教育環境の充実」です。大学院は高度な研究機関として本学の学びをリードする存在であり、そこにフォーカスを当て、その充実を図ることは、学部教育を含めた全学的な学びの向上にも貢献します。大学院への進学というと、即研究職で大学や研究機関に勤めるだけというように捉えている方が多いと思いますが、高度専門職業人として本来はさまざまな分野で活躍できる人材育成のステップのはずですし、大学院の充実化により教員と学生双方が成長できるといえます。現状の日本社会では残念ながらそこまでの認識は定着していませんが、海外ではごく当たり前の考え方ですし、私費留学生の動向や海外で活躍する卒業生を見ると、そのことが良くわかります。また、本学でも他大学同様、大学院生がTA(ティーチング・アシスタント)として学部生の学びをサポートしています。大学院の学生数を増やすこと、研究レベルを高めることは、このTAの充実に直結しますし、そのことが学部教育の充実化にも寄与します。学部教育・大学院教育の充実化が好循環を生むことになるわけです。また、かつての大学教育では座学を中心とした講義形式が主流でした。もちろん講義においても独自性を発揮させることは可能ですが、最近では、講義形式で身に付けられる多くの知識は、インターネット上で質の高いコンテンツなどを介して、簡単に入手できる時代になりました。こうした状況において、大学教育にはそれぞれ大学独自のより多面的で高度な内容が求められるようになります。その結果、学生が自分の手を動かして自ら学ぶ演習形式による学びの重要性が増すことになります。
 大学院生がTAとなり、学部生の学びをサポート
大学院生がTAとなり、学部生の学びをサポート
こうしたインタラクティブな学びの場においては質の高いTAのサポートがより大きな教育効果を発揮することになります。さらにこのことによって、授業担当者である教員にもより質の高い教育への取り組みを行う余裕が生まれてくるでしょう。また、TAは学生の身近なロールモデルでもあります。日々の授業を通じてTAとコミュニケーションを図ることで、学生は自身の将来像をイメージしやすくなり、前向きな大学生活を送る上で大きな助けを得ることができます。このように、特に目新しいことではありませんが、あらためて大学院の活性化を図ることは、研究のみならず教育の充実化に向けた非常に意味のある取り組みであることがわかると思います。
大学院充実のための取り組みについては、施設・設備面の充実化、教員や学生への支援など、さまざまな施策を検討していく予定です。たとえば、既に理工学研究科では、学内進学の成績上位者への授業料の全額または半額を給付する奨学金制度(理工学研究科 特別給付奨学金)などを取り入れ、大学院への入学者数が増加するという成果を出しています。理工学部では大学院への学内進学率が2022年度は約44%となり、併せて優秀なTAが輩出され、好循環を生んでいます。これを全学的に広めるために、理工系以外の分野においてはどのような支援体制が有効なのか、それぞれの分野の特性や背景を踏まえて検討していく必要があると考えています。

第2点めは各専門領域を結びつけ活性化させることのできる分野としての「データサイエンス・AI分野の強化」です。すでに言い尽くされていることではありますが、事象や課題が複雑化している現代社会においては、個別の学問領域だけでは解決できない問題が山積しています。その解決策のひとつとして学際領域や文理融合の取り組みがあります。また、各専門領域を結びつけ活性化させることのできる代表的な分野として、データサイエンスやAIがあります。統計やAIはそれぞれが専門分野として存在していますが、「データを扱う」ということで、コンピューターだけでなくデータの背景となっている各分野の認知・理解につながる可視化・表現の問題も含む複合的な分野といえます。まさに、客観的なデータに基づいて合理的な判断を導き出すという意味で、データサイエンスのアプローチは、人文社会系を含めた学際的な領域でも大いに力を発揮します。本学では、ようやくこれらを学部・学科の枠を超えて学ぶことができる全学共通教育システム「青山スタンダード」に組み入れることができましたので、まさに今後の展開を図っていく見通しができたといえます。
 データサイエンス・AI分野を強化
データサイエンス・AI分野を強化
今後の展開としては、青山キャンパス内にデータサイエンス教育の拠点となる小規模ではあってもユニークな理系学部設置を検討しています。そのためには関係学部を含めて丁寧な学内合意形成が必要ですが、大学を取り巻く環境についての詳細な調査の上に、人文社会系の学生が学ぶ青山キャンパスに、理系要素を併せ持つデータサイエンスの拠点をつくることで、各領域が刺激し合い、既存の学部が活性化することを目指す構想です。さらに、理工学部、社会情報学部をはじめとした広範囲のより専門性の高い情報分野の知見や取り組みによる支援を得ること、また連携を図ることで、青山キャンパスと相模原キャンパスの2キャンパスが相乗効果を図りながら発展することが期待されます。また、理系分野に代表される、研究・教育に対する、ある種のストイックな姿勢が、「真摯な学び」として学内に良い影響をもたらしてくれることも期待しています。そのことで、本学はこれまで人文社会系のブランドイメージのみが先行しがちでしたが、今後は多様な理系分野の展開に関する認知度も高めていくことで、新たな受験者層の獲得にもつなげていきたいと考えています。

第3点めは「学び直し」の取り組みです。学びとは学校を卒業した後も続いていくものですから、大学もまた「生涯にわたる教育機関」でありたいと願っています。本学では「履修証明プログラム」や「青山アカデメイア」、さらに「公開講座」といったそれぞれ趣旨の異なる多様な社会人向けの教育プログラムを設け、本学卒業生や地域社会の方々が気軽に学び直せるような機会の提供を始めています。このような取り組みは、社会連携・社会貢献の一環でもありますが、急激な少子化を踏まえた大学の将来を見据えたものともいえます。すなわち、大学で学ぶ対象者は従来の20歳前後の学生だけではなく、卒業生をはじめとする多くの幅広い社会人となることが予想されます。したがって、その際に学び続けられる場としての価値が大学の評価の重要な要素となっていくことが想定されます。そこで、短期的な社会人向けの教育プログラムの充実化にとどまらず、その魅力の延長線上に、より本格的な学びを目指すための大学院入学までリードできるような体制づくりを進めていく必要があると考えています。もちろん学部教育はその基盤ではありますが、やはりここでも大学院の充実化がカギとなりますので、何とかこの4年をかけて進めていかなければなりません。
 履修証明プログラムでは、特定の分野について体系的な学びを提供
履修証明プログラムでは、特定の分野について体系的な学びを提供
■ 全学一丸となって学生を支える体制
研究・教育に関する改革を進めるためには、それを実現させるための学内体制をどのようにつくり上げていくかも重要なテーマです。2022年から、本学では、サステナビリティレポート(中長期計画)を策定・公表し、各学部や研究科がそれぞれの中長期計画を相互に参照し合えるような仕組みを設けました。その結果、それぞれの学部がどのような問題意識を持っているのか、どのような課題を抱えているのかについて、新たな発見や問題の共有が可能となりました。さらに、他学部の取り組みを参考にして自学部の改革を進めていくこと、学部間で連携していくこと、また各学部の課題を吸い上げて大学全体の取り組みとしていくことなどが可能となりました。たとえば、学部が独自で進めている「デュアルディグリー」や「海外インターンシップ」などの国際プログラムなどについても、学部単独で進められる範囲と全学的な取り組みとしなければならない問題の切り分けができるように思います。そして、人文社会系の複数の学部が、理系分野の学びをどのように取り入れていけばよいかという問題意識を持っていることなども共有することができます。せっかくこのような取り組むべき課題が可視化されることとなりましたので、今後は運営上のさまざまな決定プロセスについても、学内の闊達なコミュニケーションを促すような工夫を進め、さらなる活性化を図っていきます。こうした地道なプロセスを積み重ねていくことが、新たな青学ブランドの基盤づくりには不可欠であると考えています。
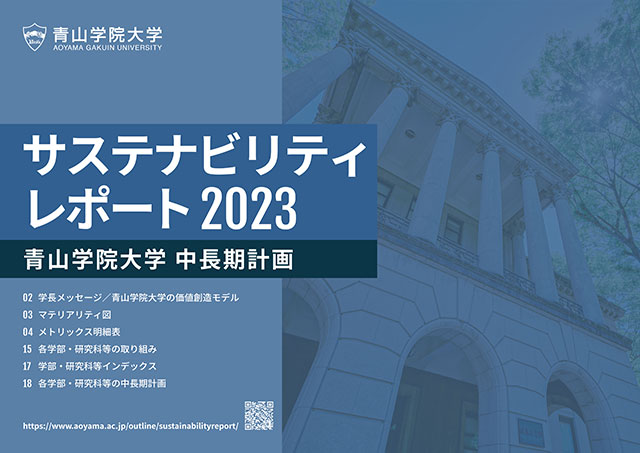 各学部・研究科等の中長期計画を掲載した『青山学院大学 サステナビリティレポート2023』
各学部・研究科等の中長期計画を掲載した『青山学院大学 サステナビリティレポート2023』
研究・教育施設といったハード面の整備を進めていくことも重要な課題です。2024年4月、青山キャンパスには新図書館棟である「マクレイ記念館(大学18号館)」が開館します。図書館機能に加え、ICT関連諸施設を配置することで、学術情報施設として総合的な学びの場をつくることができます。学生本位のものとして、さらに研究者のニーズに応えるものであるのはもちろんですが、それにとどまらず広く大学にかかわる人々のアカデミックな活動のための拠点となるでしょう。さらには、社会からの要請や時代の変化に基づき、広く社会に貢献する場となることを期待しています。一方、相模原キャンパスについては、広々としたキャンパスの中に充実した研究・教育施設と運動施設が共存しています。4学部を中心とした活動を支援することにとどまらず、学会・研究会による広範囲な研究活動やキャンパス全体を活用した地域連携イベントを通した既存施設の有効活用などを展開していかなければなりません。郊外型キャンパスならではの付加価値を生み出すことを目指し、運用面も含めた環境整備を進めていきます。
 新図書館棟「マクレイ記念館」が2024年4月に開館
新図書館棟「マクレイ記念館」が2024年4月に開館
■ 建学の精神と社会連携
個々の施策については積極的に改革を進める一方で、キリスト教の精神に基づく建学の志は、今後も大切に守り続けていくべきものです。本学は、聖書の中の言葉「地の塩、世の光」をスクール・モットーに掲げ、サーバント・リーダーたる人材の育成に努めてきました。「塩」とは目立たずとも重要な役割を果たすもの、「光」とは世の導きとなるものです。本学の学生を見ていると、「誰かを押しのけてまで成功したい」ということではなく、多くは相手に対する優しさや思いやりを大切にしており、その姿勢が校風にも表れています。時にはそれが物足りなさに映るかもしれませんが、結果としてその優しさは人間としての余裕につながり、学生たちは卒業後も社会に求められる人として大きく飛躍してくれています。そのような学生の成長を第一に考えることを決して忘れずに、大学運営を行っていきたいと考えています。
本学においては、大学としてのアイデンティティーを見つめ直すための原点が聖書でありイエス・キリストの言葉です。そこには現代に生きる者にも通じる哲学があると思います。私自身はクリスチャンではありませんが、キリスト者であるラインホールド・ニーバーが残した「祈りの言葉」を念頭に置きながら、「変えるべきところは大胆に変える一方で、変えてはいけないところはしっかりと守り抜く、その両者を見極める思慮を持つ」というメッセージを大切にしていきたいと考えています。
本学が進めている「社会連携」の取り組みも、「地の塩、世の光」の精神に基づくものといえます。本学では社会連携を推進するべく、2022年度に社会連携推進機構と社会連携課を新たに設置しました。正課科目(青山スタンダード科目)としてのサービス・ラーニングの展開、ボランティア活動支援や自治体との連携活動、産官学連携等、研究・教育の枠にとどまらない多岐にわたる分野は、「社会連携」という枠組みとしての実践ということができます。また先にご紹介した「学び直し」の取り組みもそうですし、体育会各部の活動も広く社会とつながる活動ということもできます。たとえば、なぜ大学がスポーツ振興に取り組まなければならないのかという問題提起があります。本学では、多くの学生が競技活動や競技成績の向上を通して、今後もAIでの代替は難しいであろう高度なスキルを身に付け、それぞれの所属学部での学びに対するセカンドメジャーとして位置付けて、文武両道を目指して取り組んでくれることを期待しています。また、それらはさまざまな研究分野にも通じるものですし、社会連携における貴重で有効なシーズでもあります。たとえば近年には「青山学院大学スポーツ健康イノベーションコンソーシアム」を立ち上げ、「CAS(Community Activator with Sports)プロジェクト」」としてスポーツ指導者の育成やスポーツを通したコミュニティーづくりといった取り組みも始めています。このように、研究・教育の起点として、さらにコミュニティーづくりの起点として、青山キャンパス、相模原キャンパスは積極的に社会に対して門戸を開く存在にしていきたいと考えています。こうした社会連携を通じて、地域の方々に本学の教育や研究内容をはじめとした取り組みを知っていただくことは、学内の活性化にもつながりますし、何にも代えがたい真の広報としての意味をもつことになると思います。
 陸上競技場のほか、アーチェリー場、テニスコート、フットサルコートなどを完備した相模原グラウンド
陸上競技場のほか、アーチェリー場、テニスコート、フットサルコートなどを完備した相模原グラウンド
■ 学生へのメッセージ
本学は教育研究共同体として、さまざまな取り組みを実践する場を提供しています。学生の皆さんがこれをどのように生かすかは、在学中の過ごし方次第です。ぜひ多くのことに積極的にチャレンジし、その経験を吸収・昇華してさらなる次のステップへ向けて成長してください。学生の皆さんの姿に刺激を受け、共同体としての大学もさらに良いものとなっていきます。さらに、そうした大学には意欲的な学生が集まり、卒業後は胸を張って社会に貢献していくという良い循環が生まれます。ぜひともに、成長し合える場、教育研究共同体をつくっていきましょう。

大学執行部
- 学長 稲積 宏誠(いなづみ ひろしげ)
- 副学長(学務及び学生担当) 杉本 卓(すぎもと たく)
- 副学長(総務担当・産官学連携担当) 中里 宗敬(なかさと むねのり)
- 副学長(広報及び国際連携担当) 内田 達也(うちだ たつや)
- 学長補佐(データサイエンス担当) 荒木 万寿夫(あらき ますお)
- 学長補佐(サステナビリティ・ガバナンス担当) 小西 範幸(こにし のりゆき)