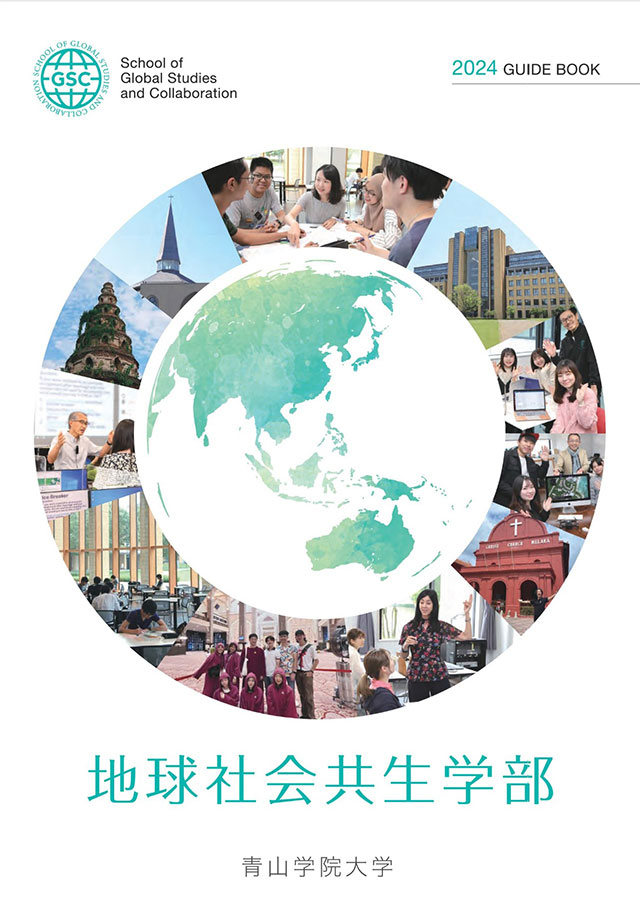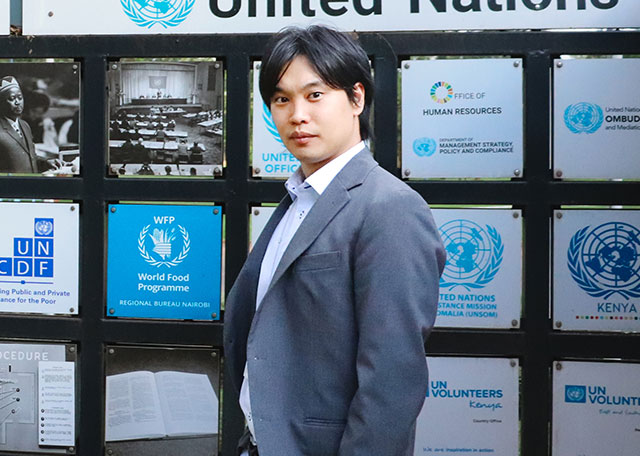学生と教員がコラボレーション
共に成長し合い、
地球規模の課題に取り組む
先行きが予測できない「VUCA※時代」と言われる今、
地球社会共生学部は、どのような人材を育成すべきか?
それぞれのスタイルでグローバルかつ
プロフェッショナルな経験を積んだ2人の先生が語り合います。
※VUCA…V「Volatility:変動性」、U「Uncertainty:不確実性」、C「Complexity:複雑性」、A「Ambiguity:曖昧性」の頭文字をとった造語で、将来の予測が難しく、先行きが不透明な状況を意味します。

松永 エリック・匡史 学部長
青山学院大学大学院国際政治経済学研究科修士課程修了。音楽家としての経験を生かし、デジタル時代を牽引するビジネスコンサルタントとして活躍。アクセンチュア株式会社、日本IBM株式会社、デロイト トーマツ コンサルティング株式会社の執行役員などを経て、2023年より現職。

堀江 正伸 教授
日本福祉大学大学院国際社会開発学研究科修士課程修了、早稲田大学大学院社会科学研究科地球社会論専攻(博士後期課程)修了。株式会社大林組東京本社勤務、バンコク駐在を経て、国際連合世界食糧計画職員として、インドネシア、スーダンなどで勤務、2022年より現職。
 徹底した英語教育や学部留学、
徹底した英語教育や学部留学、
さらに幅広く学べるのがGSCの魅力です
エリック:地球社会共生学部(School of Global Studies and Collaboration / 以下GSC)では、地球規模の社会課題(グローバルイシュー)に向き合うための「共生マインド」を育むことを目指しています。青山学院のスクール・モットーである「地の塩、世の光」、つまり社会に貢献する精神を育てるという意味でも、青学らしい学部です。専門分野を探究するアカデミックな教員と、企業などでプロフェッショナルな実務経験を積んだ教員が協働し、社会状況に合わせて進化しながら、常に新しい「地球社会共生学」に取り組んでいます。
堀江:グローバルイシューへの向き合い方も、従来は国連やJICAにスポットが当たっていましたが、これからはビジネス業界やメディア、NGOなど多様な分野の力を融合させて対処しなければならない時代で、国際協力の専門家は、企業とコラボレーションすることも考えています。GSCでは、そういった新しい考え方も含め、バラエティー豊かな教授陣のもとで幅広く学べるのが大きな特長だと思います。学生も教員もやるべきことが多く、ポジティブな意味で大変多忙ですが、その分豊かな学びを得られると感じています。
 松永 エリック・匡史 学部長
松永 エリック・匡史 学部長
エリック:段階的に学べることも特長の一つです。座学で知識を得て、タイ、マレーシアへの学部留学で学びを体感します。そして、留学の体験をまとめたり、興味のある分野をより専門的に学んだりするためにゼミナールがあります。また、留学で多様な経験をするためのツールとして、英語力を身に付けてもらうため、1年次から週に6コマの授業で、ネイティブの講師に学ぶカリキュラムを用意しています。留学先は、社会変化が著しいアジアで学ぶ意義と、学生が共通の学びを得られるという目的もあり、タイとマレーシアの協定校に絞っていますが、このアジア留学を世界で学ぶ契機にしてほしいと考えています。実際、その後、欧米に留学する学生もいます。
堀江:GSCの学生を見ていると、日常的に英語に触れていれば、英語が障壁ではなくなると感じますし、自分の考えを相手に伝えられて、相手の言いたいことも理解でき、英語で協働作業ができるレベルに成長できると思います。また、企業で国際的なビジネスに携わる場合、アジア各国の人と関わることも多いので、アジア留学の経験は強みになるはずです。私は前職でタイに駐在しましたが、現地にあまりなじみがなかったこともあり、正直なところ当初は戸惑いもありました。学生の皆さんも留学前は何かと不安もあると思いますが、留学から帰ってくると、皆さんの意識がガラリと変わっているのが分かります。
 堀江 正伸 教授
堀江 正伸 教授
 教員同士の学びや世代の違う学生からの
教員同士の学びや世代の違う学生からの
刺激で自らも成長しています
エリック:堀江先生はタイ語をはじめ、東南アジアの言語に長けていて、タイの視察に同行したとき、現地の人たちとの雑談で大笑いしたりしていて、コミュニケーションの深さに驚きました。「共生マインド」にフォーカスしたとき、現地の言葉で交流することの意味合い、大切さをあらためて感じました。
堀江:就職してまもなくタイに赴任したので、家族もいないしゴルフもやらない。そんな日本人が珍しかったのか、現地の人がいろいろなところに連れて行ってくれたんです。おかげでタイ人の友達が増えてタイ語が身に付き、日常的な買い物や、さまざまな体験を共にすることで、現地のカルチャーを体感できたと思います。学生の皆さんにも、学部留学で多くを経験してほしいです。授業で現地の文化などを学び、留学で実際に見聞きして、「先生が言っていたのはこういうことか」とか「ちょっと違うな、自分にはこう見える」など、さまざまなことを感じてほしいですね。
エリック:私は堀江先生の影響で、東南アジアへの関心がさらに深まっています。マレーシアで、私たちの生活に必須の日用品など多くのものに使われている、パーム油の原料になるヤシの広大な畑を見て、環境問題に対する意識も高まりました。
堀江:私もさまざまな分野の先生から教わることが多く、その学びが自分の専門に生かされています。パーム油にまつわる環境問題や現地の労働問題に関しても、エリック先生のご専門であるビジネス的な観点からアプローチできないかと、学生たちと新しい試みを始めています。
 インドネシア人共同研究者と堀江先生
インドネシア人共同研究者と堀江先生
エリック:分野や世代が違う人たちから影響を受け、そこから学ぶことは多いですよね。私は共に成長する「共育」をポリシーにしていて、学生からもいろいろなことを教わっています。情報発信が大事な今の時代、特にSNSを中心としたメディアの使い方は勉強になるし、学生時代に携帯電話もなかった私たちに比べて、ITやデジタルに対する感度も高く、非常に刺激になっています。「モノからコトへ」といわれるように、私たちの世代とは消費行動も違います。私が若いときは何より欲しかった自動車もシェアリングだし、モノより体験重視ですよね。社会貢献への関心も高く、ボランティア経験のある学生が多いことにも感心しています。
堀江:ウクライナへの支援に関して、日本は生活に必要な物資などを提供していますが、武器を供与する国もあります。人道支援を専門とする私の立場では、人道支援的なものと武器は相反するものと考えていますが、学生から、実は同じ効果をもたらすのではないかという質問があり、そういうとらえ方もあるのかと気づかされました。恩師から「“学者”とは教える者ではなく“学習する者”」と言われたことを肝に銘じています。教科書に書いてある知識は学生より豊富かもしれませんが、学生との交流から学ぶことも多いです。
エリック:学生との交流で心がけているのが「共感」です。端的に言えば、教員と学生の関係ではなく、コラボレーションです。対等な会話の中で互いの知見を共有すると、気づきや学びがあります。例えば、私はウォークマンを作ったソニーが発展してきた過程を知っていますが、その時代を知らない今の学生と、ソニーに対する互いのイメージを共有することで、新たな発見があるんです。
 学生たちと語らうエリック先生
学生たちと語らうエリック先生
 「共生マインド」を体得し、人の幸せのために
「共生マインド」を体得し、人の幸せのために
活動できる地球市民になってほしいです
エリック:ビジネスにおいても共感力は必要で、グローバルかつ、さまざまな領域の人と連携して仕事を進めるとき、共感力がないとチームが成立しません。アジアパシフィックの各国の人が集まったときに、お互いのマイナスイメージを語り合うセッションを展開したことがあって、あれこれ話して仲良くなるにつれ、みんなが「このイメージは、あくまで国同士のことだよね」と気づき、個人レベルで腹を割って話せば、国を越えて共感できると感じました。
堀江:タイに赴任する前、タイ人はみんなパクチーが好きだと思っていましたが、実は嫌いな人も多かったんです。ステレオタイプな物の見方にとらわれていることも多いですよね。また、国連では世界各国の人たちと一緒に仕事をするので、コミュニケーションについて懸念もありましたが、例えば、食糧不足の地域にいかに食糧を供与するかなど、共通の目標があることで共生できることも実感しました。私がタイに赴任した当時、周りの人から「郷に入れば郷に従え」と言われました。相手と自分の違いを理解して、相手の文化や習慣に沿って行動するということですが、今はそこから一歩進んで、お互いを尊重した上で共生することが求められる時代だと思います。
エリック:最も関心がある課題はダイバーシティです。私がもともといた音楽の世界に男女の区別はなかったのに、企業に入ってみると、女性が重要な役職に就くことは稀で、結婚や出産時に辞めざるをえない状況に違和感がありました。その後、アメリカの企業で働いていたときの上司は女性でしたし、女性社長の会社もあって、日本との違いを考えさせられました。ジェンダーで悲しい思いをしている友人も見てきたので、みんなが笑顔で共生できる社会を作りたいし、GSCでも積極的に取り組むべき課題だと思っています。
堀江:グローバルな課題に対処しているのは、国連やWHOなど、あくまで国の枠組みを基盤としている機関です。ボーダーレスな課題に向き合うとき、それだけでは限界が来ることは、コロナ禍が如実に物語っていますよね。よりグローバルなユニットを作らなければならないし、そのために必要なのが「共生マインド」です。今はまだ自分のやりたいことが分からない受験生の皆さんも、幅広く学べるGSCで、自分がどのような課題解決に貢献できるか、見つけてほしいです。
エリック:最近は日本でも、企業が社会の課題に向き合う必要性が問われていますが、アメリカでは以前から、企業は利益を追求するだけでなく、社会貢献しなければならないという考え方を提示していた会社がありました。GSCの卒業生には、日本でもこの考え方がスタンダードになるような活動をしてほしいです。企業に就職する人だけではなく、アーティストなども同じです。例えば廃材を利用して作品を作るなど、自己表現のためだけではない、誰かの幸せを意識した活動をしてもらいたいと思います。将来、人のためになることがしたいと考えている受験生の皆さん、GSCで一緒に成長しましょう。
地球社会共生学部 インタビュー(AGU LiFE)
*掲載されている人物の在籍年次や役職、活動内容等は、特記事項があるものを除き、原則取材時のものです。